機能安全連載 完結
おかげさまで、CQ出版 インターフェースでの機能安全連載が完結いたしました。ご購読いただいた皆様、ありがとうございました。2年にまたがる連載のため、インターフェース記事CDが2015年と2016年にまたがりますが、ぜひ通読をしてみてください。出版リクエストも編集部まで。(笑)
2015年8月号 #1回 「機能安全」と「本質安全」
2015年9月号 #2回 「リスク」「安全」用語の定義
2015年10月号#3回 「リスクマネージメント」
2015年11月号#4回 「構想設計」
2015年12月号#5回 「FMEA」
2016年1月号 #6回 「購入部品のリスク評価」
2016年2月号 連載お休み
2016年3月号 連載お休み
2016年4月号 #7回 「システムの安全性を診断する方法」①
2016年5月号 #8回「システムの安全性を診断する方法」②
2016年6月号 #9回「システムの安全性を高める多重化多様化」
2016年7月号 連載お休み
2016年8月号 #10回「機能安全は構想設計が大切」
2016年9月号 #11回「機能安全のソフトウェア開発」
2016年10月号#12回「プロセスとトレーサビリティ」
架空の恒星間宇宙船を例にもちいて機能安全を気楽に知ってもらおうというのがコンセプトです。
この連載では機能安全IEC-61508の設計開発プロセスに沿って解説を進めます。
CQ出版 インターフェース
続きを読む
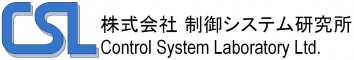

最近のコメント